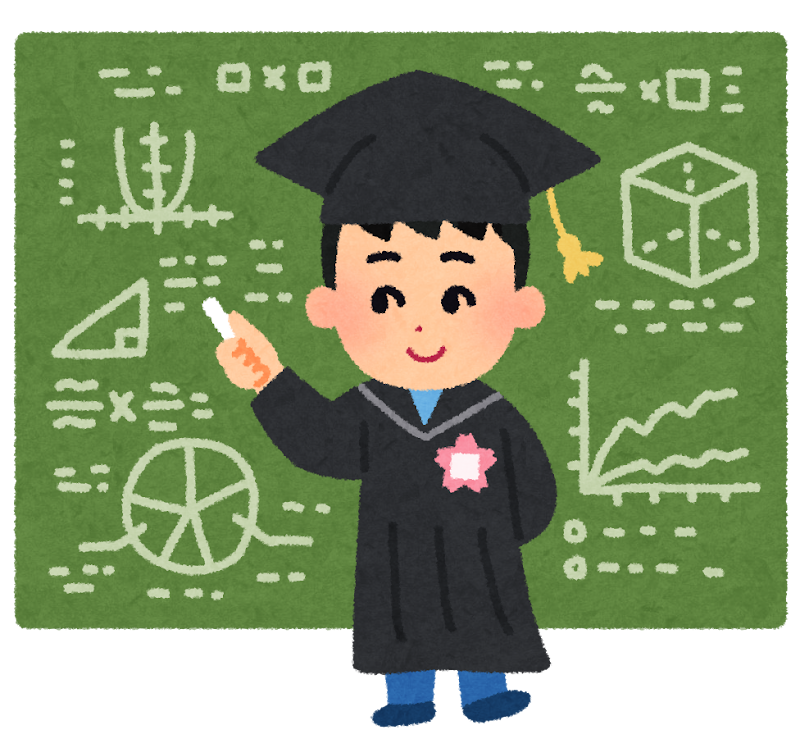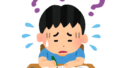ぶながやっ子ハウスが目差す「でぃきやー」は「日常生活の中で多くの体験を積み、そんな体験の中から多くのことを主体的に身につけているからこそ学校の成績も良い子どもたち」のことでした。
それでは「でぃきやー」が是非とも身につけるべきこととは何でしょうか。今回のブログでは、そのことについて考えてみたいと思います。
「思考力」
「でぃきやー」にとって「思考力」、自分で主体的に物事を考える力は欠かせないでしょう。この「思考力」について、もう少し詳しく考えてみたいと思います。一口に「思考力」と言っても、実はその中に様々なものが含まれているのではないか、とyamaは考えています。
「論理的思考力」と「想像力」
「思考力」の中でも「論理的思考力」は非常に重要です。「論理的思考力」については以前のブログ「間違い直し 2024.01.23」や「学力を育てるのは机の上ではありません」でも触れていますのでそちらをご覧ください。この「論理的思考力」と同じくらい重要なのが「想像力」だとyamaは考えています。「論理的思考録」と「想像力」には非常に深い関係があります。「論理的思考力」が充分身についていなければ「想像力」も満足には発揮できません。「妄想力」になってしまいます。
「想像力」には、原因から結果を予測する力と、結果から原因を推測する力、の両方がありますが、いずれも、多くの因果関係を経験していればいるほど、力を発揮しやすくなります。ですから、やはり「想像力」にも体験は重要なのです。この「想像力」は文章読解に非常に影響します。
算数の文章問題が苦手、国語の長文読解が苦手と言う子どもたちの何割かは「想像力」が充分には身についていない子どもたちです。そんな子どもたちに「文章をよく読みなさい」と指導しても、ほとんどの場合、あまり効果は期待できません。文章を何度も読んで考えさせるよりも、可能な限り、文章に書かれていることと同じ体験をさせてやったり、できるだけ似ている体験を思い出させたりしてやった方がずっと効果的です。体験させることが難しい様でしたら、絵に描いてみたりマンガにしてみたりして説明してあげてみてください。中には、「リンゴを食べたら、食べた分だけ『リンゴの数が減る』」ことすら想像できない(想像しようとしない)子どももいるのです。
「試行錯誤する力」
「論理的思考力」が充分に身につき「想像力」も育ってくると、その次に「試行錯誤する力」が芽生えてきます。「試行錯誤する力」は、少し複雑な問題や難しい問題を解く際に不可欠です。

例えば、小学4年生で習う「2ケタの数で割る割り算の筆算」は「試行錯誤する力」がなければ解くことができません。間違うことを前提に考えなければ正解にたどり着けません。間違いや失敗を恐れてしまったり「試行錯誤する力」が不足していたのでは、解くことができないのです。何度も試行錯誤を繰り返すうちにだんだんと慣れると勘が働くようになりますが、そこに辿りつく前に力尽きてしまう子どもたちは、かなりの数だになるでしょう。これが、いわゆる「小4の壁」の原因の1つではないか、とyamaは考えています。遅くとも小4になる前に、「試行錯誤する力」の芽生えを経験させておいてやりたいものです。幼い頃からなぞなぞやパズルに親しませておくのもお勧めです。
2025.04/20