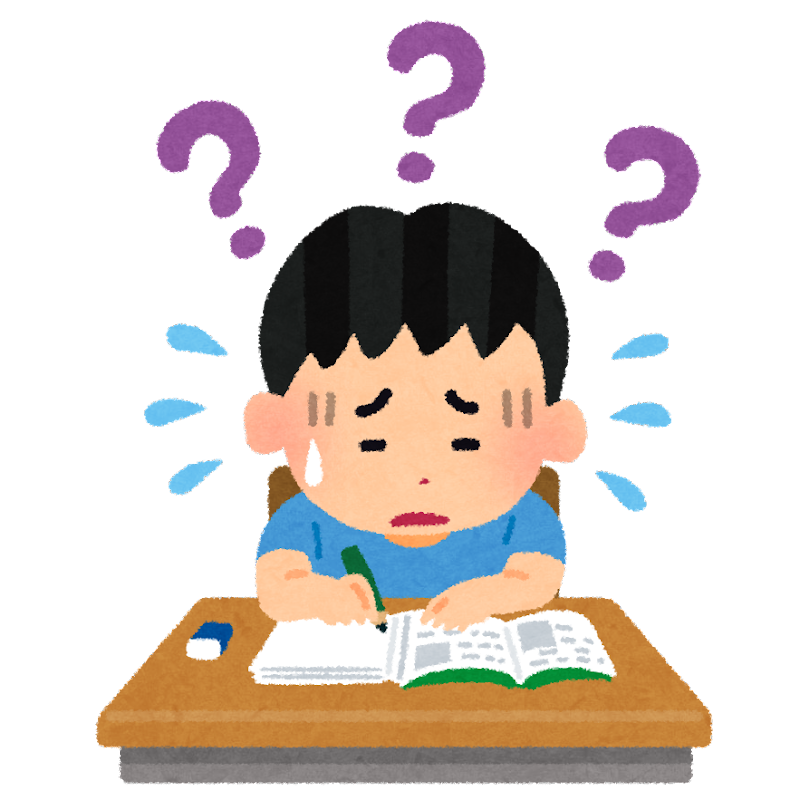久しぶりの間違い直しシリーズです。しばらく書いていませんでしたが、子どもたちの間違いの画像も溜まってきましたので、再開してみたいと思います。
成績が悪いのは、わからないからではありません
次の画像は、漢字が苦手な子どもたちのために、ぶながやっ子ハウスで準備した漢字練習用のプリントです。
20250402_151
少し、この答案を眺めてみてください。どの様にお感じになったでしょうか。
この答案を見たとき、yamaは20年ほど前のある報道を思い出していました。ちょうど文科省が全国学調査のテストを始めた頃のことだったと記憶しています。残念なことに、沖縄の中学生の正答率が低いことが話題になったのですが、他府県の子どもたちと比べて特にある点が目立っていた、と言うのです。
それは、他府県の子どもたちの答案に比べて、回答欄に空白が目立った、と言うものでした。それも少しの違いではなく、パッと見ただけでもわかるくらい、何倍も多かったと言うのです。さらに、記号を選ぶだけの選択肢の問題ですら、空白が目立った、と言うのです。その後、県立高校入試でも同様の傾向が見られることがわかったそうです。
厳密に言えば、空白は「無回答」ですから、間違いではありません。ただ、得点できない、と言う意味では間違いと同じです。むしろ、「それ以上に悪い」とも言えるかもしれません。
大切なのは非認知能力
先ほどの答案の画像をもう一度眺めてみてください。yamaが気になるのは、③、⑨、⑫、⑬の問題です。下の漢字の中から選んで写せばいいだけなのに、写していません。選択肢の問題を選ばないのと同じです。考えなくても解くことはできるのに、解いていないのです。⑩も気になります。漢字を写し間違えてしまっています。
確かに、正しい漢字を知っていれば、この様な間違い(無回答)はしないでしょう。ですけれども、重要なのはそこではありません。
「運も実力のうち」などと言うように、まぐれでも正解は正解です。その子の実力ではないかもしれませんが、たまたま当たった正解でも結果には影響します。空白の多い答案用紙を出すと、それだけで、成績は悪くなってしまうのです。
それでは、何故、回答欄が空白のままにしてしまうのでしょう。その理由には、非認知能力が大きく関わっているのではないか、とyamaは思います。
失敗を恐れさせないためには
非認知能力のうち、自己肯定感や自己効力感が低いと、失敗を恐れたり、自信が持てなくて諦めてしまったりします。どんなに「勉強」や「学習」をさせても、それだけでは足りません。その前に自己肯定感や自己効力感を伸ばしておいてやらなければ、せっかく身につけた「勉強」や「学習」も、その成果を充分に発揮することはできません。極端な言い方をすれば、「勉強」や「学習」すること自体が無駄になってしまうのです。特に自己肯定感や自己効力感が低い場合には、逆効果になってしまうことも多いので、注意が必要です。もし、失敗を恐れない自己肯定感の育て方に興味がおありでしたら、失敗は成功の母の記事をご覧ください。
向上心と意欲
答えを書かない、もう一つの理由は、向上心や意欲が足りないせいでしょう。向上心や意欲(ヤル気)は自己肯定感や自己効力感の上に育つので、子どもに向上心や意欲(ヤル気)を持たせたければ、やはり、まず自己肯定感や自己効力感を育ててやるべきです。ただ、それだけでは足りません。想像力も欠かせません。ただ、ここで言う想像力は、物語を聞いて想像したり、荒唐無稽なことを想像する力ではありません。自分の未来や将来のことを論理的に考えて予測する力のことです。
この様な想像力を育てるためには、自分と言う存在のことを詳しく知らなければなりません。そのためには、自分を客観的に見つめる習慣・姿勢が必要です。その様な習慣・姿勢を育てるためには、子どもたちが、周りから干渉されずに自分自身で行動する経験をできるだけたくさん、積み上げてやらなければなりません。干渉されたり、あれこれ手出し口出しされてばかりいると、自分を見つめる(自分の行動がどの様な結果に結びついたか、を知る)ことはできません。想像力が足りない子どもは、未来や将来は自分の行動によって変わることが、充分には身についていませんから、向上心や意欲(ヤル気)を持てるはずがありません。
学力の前につけてやるべきこと
成績の良し悪し、学力に様々な非認知能力が関わっている、と言うお話をしてきました。
他のブログでも書きましたが、子どもたちの学力を高めたければ、机の上で勉強や学習だけさせても効果は期待できません。まず、その前に、非認知能力を育て引き出してやる必要があります。それを無視して勉強や学習ばかりさせていると、逆効果になってしまうことも少なくありません。非認知能力を充分に育てないまま、子どもたちに勉強を無理強いすることだけはやめて頂きたい、とyamaは思います。