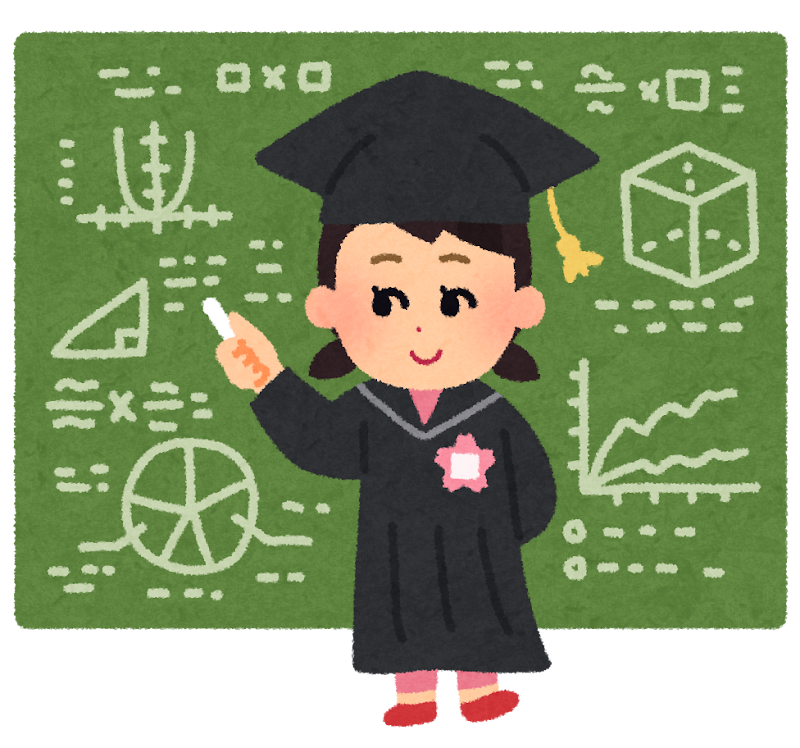前のブログで、「でぃきやー」について触れました。沖縄の方言で「でぃきやー」とは、「頭が良い人」とか「成績が良い人」などの意味だそうです。
小学校で習うこと
小学校で習うことのほとんど全ては、子どもたちが体験の中で身につけるべき内容ばかりです。極端な言い方をすれば、体験の中で身につけるべきことを完璧に身につけていたならば、わざわざ教室でまで学習する必要はないことばかりです。
国語の漢字や言葉も、学校の教科書で学ぶより、いろいろな書籍などから学んだ方が質も量も豊富に学ぶことができます。算数で学ぶ四則演算も生活に密着したものばかりです。「割合」や「速さ」なども同様で、教科書の説明を理解するよりも、実生活の中で感覚的に身につけた方が、よっぽど応用が利きます。公式だけを覚えさせてむりやり解けるようにしてやっても、結局、身にはついていないので、いつまで経っても消化不良のような気分になってしまいます。理科や社会にしても同様です。昆虫や生き物に興味がある子どもにとっては、小学校の理科で学ぶ程度の内容は、すでに身についてしまっているでしょう。歴史や偉人に興味がある子どもについても同様です。教科書には出てこないような人物の名前を知っていたりします。

「頭が良い」、「成績が良い」のは何故?
世に出てしまうと少し話が違ってくるのですが、小学生の間でしたら、「頭がよい」≒「学校の成績が良い」と考えても良いのではないでしょうか。少なくとも、「頭がよい」と「学校の成績が良い」の間には密接な関係があると言えるでしょう。であるならば、「でぃきやー」の第一条件は「学校の成績が良いこと」と考えても良さそうです。
しかし、「公式や解き方だけを覚えているので解くことはできるが、消化不良を起こした様に納得はできていない」状態では、本物の「でぃきやー」ではない様に思います。そんな状態になってしまうのは、体験の中で身につけるべきことを身につけていないからではないでしょうか。子どもたちを「でぃきやー」に育てたければ、日常生活の中の体験を大切にするべきです。日常生活の中から身につけるべきことを主体的に身につけていくことができれば、学校で習うことくらいは、簡単にこなすことができるはずです。
ぶながやっ子ハウスが目差す、本物の「でぃきやー」とは、「ただ学校の成績が良い」だけでなく、「日常生活の中で多くの体験を積み、そんな体験の中から多くのことを主体的に身につけているからこそ学校の成績も良い子どもたち」とでも言えるでしょうか。
体験較差
近頃、インターネットなどでも、子どもたちの「体験較差」が話題となることが増えました。そんな記事を読みながら、yamaはいつも、違和感を感じていました。その様な記事で扱われる「体験」のほとんどは、「非日常的な体験」や「塾や習い事に通わせる体験」など、日常や生活からかけ離れ、金のかかる「体験」ばかりだからです。その様な「体験」はむしろ、子どもたちを「でぃきやー」から遠ざけてしまうのではないか、とyamaは考えています。教育関連業界がスポンサーになって、子育てに少しでも多く金をかけさせよう、としているのではないか、と勘ぐってしまうほどです。
以前、子どもたちの健全な発育には親子の共通体験が必要である、と書きましたが、親子の共通体験は、日常生活の中でこそ育まれるものです。「非日常的な体験」や「塾や習い事に通わせる体験」の中ではなかなか育ってはこない様に思います。そんな「特別な体験」を用意するくらいなら、まずは日常の中の体験をもっと大切にするべきではないか、とyamaは考えます。そんな「特別な体験」のために、大切な日常を疎かにしないでください。
 |
 |